動物のサルを指して、エテ公なんて呼ぶのを聞いたことがある。
ただ疑問なのは、エテ公とサルとでは1文字もかすっておらず、お互いの言葉にどういう関係があるのか。
あくまで説だが、肝心の答えは猿とは何も関係がなく、昔の人々のゲン担ぎから生まれた言葉らしい。
もともとは「得て」から

一説によると動物の猿を別字におきかえた「去る(さる)」の言葉が、人との別れや物を手放すことを連想させるため「得る」へと変化したのが由来の1つになっている。
つまり言葉のゲン担ぎ。
これがさらに得て・エテへと変化し、また得手という風に、物事が得意という意味も持つようになった。
また語尾に「公」を付けるのは、親しみまたはさげすみを込めて呼ぶ「擬人化表現」が使われているらしい。
用法としてのエテ公はおサルさんそのものに対して使われたり、あるいは人へのあだ名として使われる。
さらに良い意味
「得手」の意味から派生し、他人より秀でた才能で「勝る(まさる)」という言葉から、さらに猿つながりで「真猿(まさる)」とシャレっぽい言葉に変わったという話もある。
ただし、リアルで使うようなシチュエーションはほぼなさそうだ。
「キミは真猿だ!!」
「えっ!?(オレ、テツヤなんだけど……)」
誉めたつもりでいきなり使ったとして、こういうことになるかは不明(ほぼ通じないと思われる)。
一見、どれもただの言葉遊びのように思えるが、先ほどの得るも含めて、いずれも良い意味の言葉説になっている。
ただ「エテ公」とすると、やはり良い言葉には到底聞こえないが……。
悪く聞こえるのは
恐らく「公」という言葉が原因だと思われる。
エテ公などに使われる場合の公は、それこそ親しみやさげすみを込めて相手を呼ぶ、擬人化表現の1つ。
よって「おいエテ公!」などの言い方は、何となく人を猿に見立てて、もしくは猿そのものを下に見て使うイメージである。
たとえばこの言葉で人を呼んだとしたら、言った方が親しみをいくら込めていても、相手はバカにされたと思うはずだ。
なお公には「公爵」など、高貴な身分を指す意味もあるが、ここでの公はあくまで侮蔑的な意味合いのものとなっている。
擬人化表現ってのは人じゃないものを人に見立てるっていったら分かりやすいかな。
たとえば、ファンタジー映画に出てくる燭台とかポットがしゃべって動いたりするの。
ああいうのさ。
コチョンどのも人の言葉をしゃべれるから、ある意味擬人化ではないのか?
そこツッコむとメタな話になるし、ややこしくなるからやめてよ……。
まとめ
「エテ」は「去る」の意味を嫌った人々が得て・得手という言葉に変化させたという説から考えて、もとは悪い意味の言葉ではなかったことが分かる。
しかしそこに高貴な身分を示す言葉「公」のたった一文字を足しただけで、悪い意味の言葉に転じてしまうのが日本語の複雑なところだ。
もっとも本物のサルをエテ公と呼んだところで、相手に言葉が通じないからまだしも、どんな状況でも人間に対してエテ公と呼ぶのはNGである。
まだ謎が残っているんだが、そもそもエテ公はいつ出来た言葉なんだろうな。
最初に言葉を思い付いた人間は、はたして本物の猿に対して使ったのか、それこそ人を猿に見立ててあだ名の様に呼んだのか……。
それはボクも気になって調べたけど、確かに具体的な出どころまでは分からなかった。
響きから近年出来た言葉じゃないだろうけど、これはいずれ追加調査の必要があるかもね。
……話ちょっと変わるんだけどさ、昔の商家の人は「去る」を、朝の時間の忌み言葉だから嫌っていたって話もあるみたい。
ちなみに忌み言葉って不吉で縁起が悪い言葉のことよ。
今回の話の去る→得ると何か関係があるのかもね。
猿つながりの話であれば、私のような忍びは「軒猿(のきざる)」と呼ばれることもあるぞ。
忍者って猿のように身軽だし、軒下の暗い所に潜んでお仕事してそうだもんね!
確かに身軽でないと務まらないが、私は猿ではなく人間だぞ!
ただのたとえなんだけど。
つうか自分で振った話だよね
素でいってるのソレ?
了。
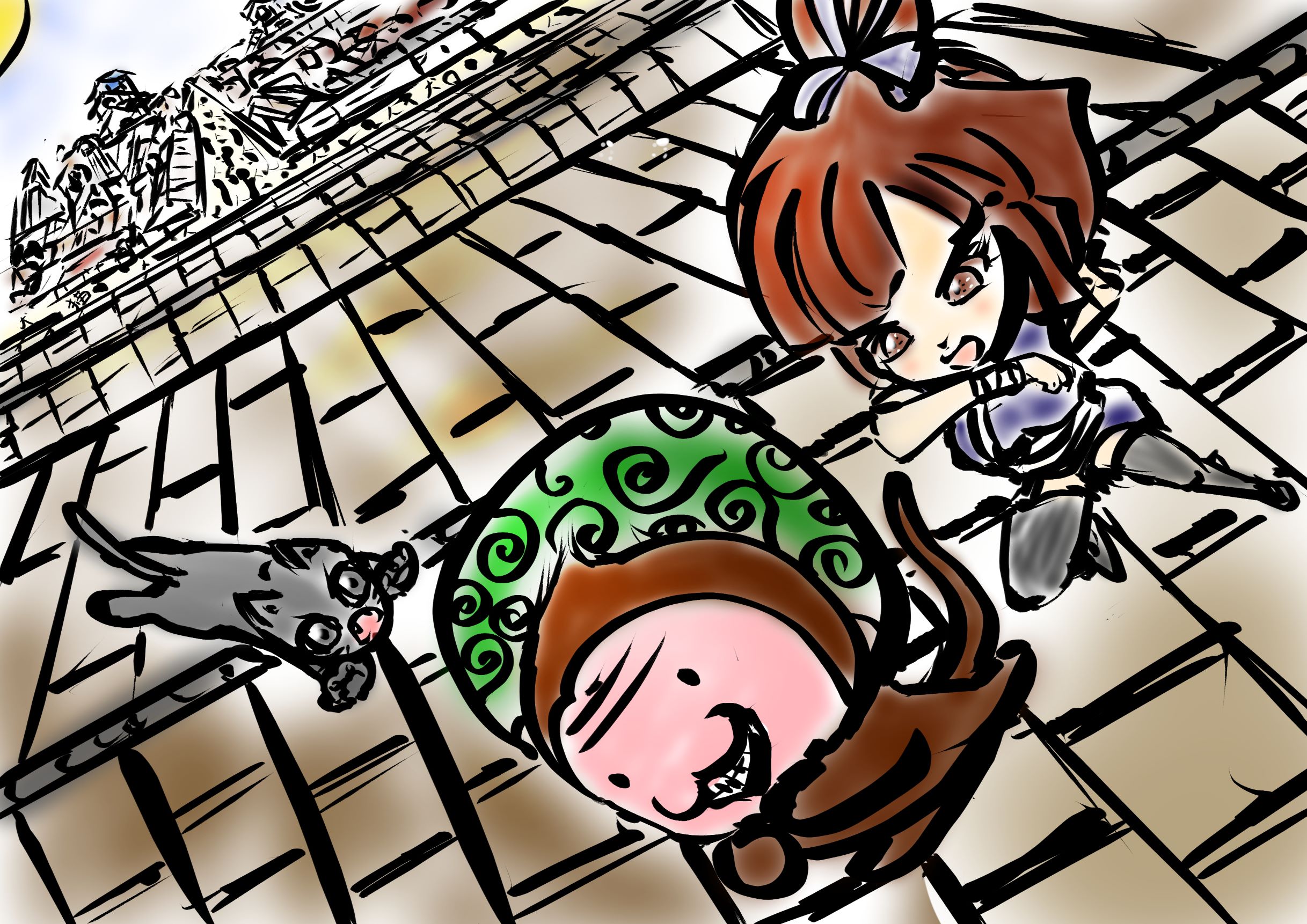


コメント